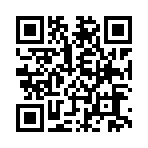2008年06月30日
役員給与
こんにちは。会計士・税理士の永野です。
最近雨が続いていますね。早く晴れてスカッとした天気にならんかなと思っているのですが。では、今日は以前受けた税務上の相談で基本的なことですが、ベンチャー企業の方にもお役に立てそうな内容を。
役員給与の話です。ベンチャーを立ち上げられた方は自分の給与としての取り分をどうするか考えられることも多いと思います。例えば、会社は6月の定時株主総会において想定より業績が良く、役員に支給する定期給与を増額する決議をし、期首の4月から遡って4月~6月分の増額分を7月に一括して支給することにしたとしましょう。本来、役員に対する給与も次の①~③の内容であれば法人税法上損金に算入することができます。つまり、①定期同額給与(支給時期が1か月以下の一定期間であり、かつその事業年度の支給額が同額である給与)、②事前確定届出給与、③非同族会社における利益連動給与のいずれかに該当する場合です。しかし、会社が①に合致するよう毎月同額の給与を役員に支給していたとして、4月~6月の増額分を一括支給してしまえば、①を満たさなくなるのでは?との問題が生じます。結論を申し上げると、遡って既に終了した役員の職務に対する給与増額分は税務上損金の額に算入されず、その分法人税が減少することはないということです。ですので、会社の損金扱いになると思って、増額支給したにもかかわらず、その分利益は減少し、けれど増額分に対応する税金の支払いは必要ということになりますので、法人における役員給与の扱いは十分に注意が必要です。
しかし、ベンチャー企業って目いっぱい頑張ったら会社の利益も出て、それに比例して役員が多く報酬をもらって然るべきなのに、定期同額給与or事前確定届出給与であれば獲得するであろう利益に関係なく役員の給与は事前に固定・・・って何かベンチャー企業には馴染まないというか、一部のサラリーマン大企業以外ではその発想はありえないという違和感を感じずにはいられませんね。
【追伸】以前ご紹介したNHKドラマ監査法人第3回・・見たんだけど、わかりづらい箇所があったと伺ったので、蛇足ですが(細かい箇所は抜きにして)注釈を書き連ねます。
時代背景としては平成14年~15年あたりと推測されるのですが、東都銀行と監査法人の監査現場でのやりとりの中で、貸出先を正常先から破綻懸念先など区分を変更することにより自己資本比率が4%を下回るとか・・・そんなやりとりがなされていました。
本来、各金融機関は貸出先の資産内容等を査定し、回収に懸念がある貸出金に対し、貸倒引当てを行わなければならず(最大100%)、特に危なっかしい会社(飛鳥屋など)に貸出をしている場合、この不良債権の自己査定次第で金融機関の引当額(=費用)が増加する→剰余金が減少する→自己資本比率が下がるという構図になります。そして、ジャパン監査法人の会計士は東都銀行の自己査定の結果の引当額が不足しているので、積み増しする必要があると指摘していたのです。また、金融機関の経営の健全性を確保するために、各金融機関には上記の自己資本比率が4%以上(国内基準)であることが求められ、これを下回ると経営改善計画の提出・実行など、最悪のケースでは業務停止命令が下されるなど、金融機関にとっては重要な指標となっており、東都銀行が最後までこの指標に拘ったのはこのような経緯があるからです。以前、銀行の国有化などの言葉が紙面を飾りましたが、それと近似した状況です。
そうすると、多分、その当時話題に上がった金融機関やそれに伴い適切な監査を行っていたのか疑問視された監査法人(フィクションではなく、ある意味事実)がモデルになっているのだなぁと推察されます。脚色されたドラマですので、現場でそんなことはしないよ(例えば、相手先会社に出向いて反面調査のごとき聞き取りをすることなど)と思う反面、過去の時代の潮流をシビアに描いているなぁと感じるところでもあります。
最近雨が続いていますね。早く晴れてスカッとした天気にならんかなと思っているのですが。では、今日は以前受けた税務上の相談で基本的なことですが、ベンチャー企業の方にもお役に立てそうな内容を。
役員給与の話です。ベンチャーを立ち上げられた方は自分の給与としての取り分をどうするか考えられることも多いと思います。例えば、会社は6月の定時株主総会において想定より業績が良く、役員に支給する定期給与を増額する決議をし、期首の4月から遡って4月~6月分の増額分を7月に一括して支給することにしたとしましょう。本来、役員に対する給与も次の①~③の内容であれば法人税法上損金に算入することができます。つまり、①定期同額給与(支給時期が1か月以下の一定期間であり、かつその事業年度の支給額が同額である給与)、②事前確定届出給与、③非同族会社における利益連動給与のいずれかに該当する場合です。しかし、会社が①に合致するよう毎月同額の給与を役員に支給していたとして、4月~6月の増額分を一括支給してしまえば、①を満たさなくなるのでは?との問題が生じます。結論を申し上げると、遡って既に終了した役員の職務に対する給与増額分は税務上損金の額に算入されず、その分法人税が減少することはないということです。ですので、会社の損金扱いになると思って、増額支給したにもかかわらず、その分利益は減少し、けれど増額分に対応する税金の支払いは必要ということになりますので、法人における役員給与の扱いは十分に注意が必要です。
しかし、ベンチャー企業って目いっぱい頑張ったら会社の利益も出て、それに比例して役員が多く報酬をもらって然るべきなのに、定期同額給与or事前確定届出給与であれば獲得するであろう利益に関係なく役員の給与は事前に固定・・・って何かベンチャー企業には馴染まないというか、一部のサラリーマン大企業以外ではその発想はありえないという違和感を感じずにはいられませんね。
【追伸】以前ご紹介したNHKドラマ監査法人第3回・・見たんだけど、わかりづらい箇所があったと伺ったので、蛇足ですが(細かい箇所は抜きにして)注釈を書き連ねます。
時代背景としては平成14年~15年あたりと推測されるのですが、東都銀行と監査法人の監査現場でのやりとりの中で、貸出先を正常先から破綻懸念先など区分を変更することにより自己資本比率が4%を下回るとか・・・そんなやりとりがなされていました。
本来、各金融機関は貸出先の資産内容等を査定し、回収に懸念がある貸出金に対し、貸倒引当てを行わなければならず(最大100%)、特に危なっかしい会社(飛鳥屋など)に貸出をしている場合、この不良債権の自己査定次第で金融機関の引当額(=費用)が増加する→剰余金が減少する→自己資本比率が下がるという構図になります。そして、ジャパン監査法人の会計士は東都銀行の自己査定の結果の引当額が不足しているので、積み増しする必要があると指摘していたのです。また、金融機関の経営の健全性を確保するために、各金融機関には上記の自己資本比率が4%以上(国内基準)であることが求められ、これを下回ると経営改善計画の提出・実行など、最悪のケースでは業務停止命令が下されるなど、金融機関にとっては重要な指標となっており、東都銀行が最後までこの指標に拘ったのはこのような経緯があるからです。以前、銀行の国有化などの言葉が紙面を飾りましたが、それと近似した状況です。
そうすると、多分、その当時話題に上がった金融機関やそれに伴い適切な監査を行っていたのか疑問視された監査法人(フィクションではなく、ある意味事実)がモデルになっているのだなぁと推察されます。脚色されたドラマですので、現場でそんなことはしないよ(例えば、相手先会社に出向いて反面調査のごとき聞き取りをすることなど)と思う反面、過去の時代の潮流をシビアに描いているなぁと感じるところでもあります。
Posted by ayamizu at 17:07│Comments(0)
│パース先生