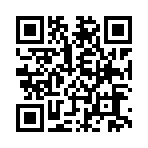2008年09月27日
人の心が動く瞬間
今年もイノベーション・ジャパンに出展しました。昨年はお世話になっている知的財産本部のブースの一部に出させていただきましたが、今年は、大学発ベンチャーゾーンに出展いたしました。実は、数か月前の申し込みをする時点では、「出展なんかに時間を取られる余裕はない」とも思っていました。しかし、ご支援をいただいている方々に現状報告をするという意味でも出展することにしました。慌ただしい数か月が過ぎ、9月3日には起業、9月8日に具体的な有報検索サービスの開始、商品としてのLPO-Mindexシステムの完成、そして9月16日からのイノベーション・ジャパン出展というように、結果的にはとてもいいタイミングでの告知となりました。
昨年の出展でもいろんな方々に出逢うことができました。今年の出展でも昨年以上に嬉しい出会いがありました。昨年は、ブースに来ていただいた人を捕まえ「1時間以上拘束して講義をしてしまった」ということを反省し、今年はポイントを押え(自分を抑え)商品の説明に徹しました(のつもり)。技術や理屈は、聞かれたときに聞かれたことだけを説明しました(のつもり)。具体的な商品がなかった昨年と、具体的な商品(2つしかないですが)があること、が大きな違いではあります。
いくらでも説明したい気持をぐっと押え出来るだけ手短に説明した後、ブースに来ていただいた人の顔を見ていますと、雲の上を見るような表情になる方が何人かおられました。最初はあれっ?外したか?と思い不安になりました。説明した後に、名刺を頂きどんな仕事をしてあるか伺ってみたら「雲の上」に何があったか少し分ってきました。それは、「この技術、システムをうちが今困っているアレに使えないか、、、、」と考えてあるのでした。つまり、説明させてもらった後に、聞いた人の目玉が上向きになりきょろきょろする瞬間が、役に立かもしれないと思ってもらえた瞬間だったのです。その瞬間に、他人の話を自分の話として考えてもらえるようになった、と感じました。具体的なビジネスはまだまだですが、人の役に立てることを嬉しく感じることができた貴重な経験でした。
2008年09月25日
“社員の1行報告が会社を変える” を読んで

まず最初に特筆すべきは、経営コンサルタントが口にし、中小企業経営者の大半が“やるべき”と“やれば結果が出る”と理解していることを、きちんと筋道を立てて実行したことに敬意を表したい。
ちなみに私は、“愚直に、地道に”をモットーにしておりますます其の意を強くしたところです。
サイバーマニュアルの発想は、たぶんに社外取締役の人からの意見が反映されているのかと想像しています。
この経営改革に着手されたころ、米国では不況でもあり大企業も大きく変貌することを余儀なくされ、いろんな考え方や手法が導入されました。
会社の持つ全資源、とりわけ社員一人ひとりの体の中にのみ埋もれている知見・経験をいかに顕在化させ、活用すべきかが大きな経営課題になっていました。Center of Excellence(COE)として各社員の持つ貴重な資産を一箇所に吸い上げて一元化し、そして可視化し全社で共有する考え方が生まれてきました。
しかしながら、いままでの文化になれた社員にとって“変化する”ことは自己否定にもつながり、失業にもつながると警戒する人もいたりで、さまざまな波紋を起こすことは容易に想像できます。
そういった社員の気持ちを汲みながら、新しい企業文化を植えつけ、育てることは一筋縄ではいきません。
著書の中でブレーンストーミングを含むいろんな形で社員の意識を変えていくところは圧巻です。社員に消極的にあたらしい考え方、やり方を受け入れさせるのではなく、参加意識を高揚させたところが肝ではないでしょうか。社員の参加意識・責任感(Ownership)は重要と認識されていたはずです。
社内を財務状況も含め透明にすれば、社員のひと一人ひとりが自分の貢献度を確認でき従って参加意欲も増すのは当然です。にもかかわらず社内を透明にし、絶えず透明度を上げることを恐れる経営者が意外に多いのも事実です。
結局は経営者と社員の信頼関係に帰趨するのでしょうか。
今回書に著せるほど“うまく”いったことには、理由があると思います。
私が考えるところをいくつか挙げてみましょう。
まず危機感です。やはり雇われの社長ではない創業者一族の抱く危機感はDNAも相伴って説得力があります。真剣味、まさに真剣での勝負を迫る迫力があったのではないでしょうか。
その危機感を受け止める役員・社員もまた今回のケースはふつうの中小企業とは異なっていたのではないでしょうか。それは先代の社長〔創業者〕が、古参の役員や社員との間に確固たる信頼関係を築いてきていると想像しています。
現社長の抱く危機感を全社で同じような度合いで共有できたと考えます。
もうひとつは、社員の人が海外に研修に行ったり、外国人の社外取締役がいたりグローバル化が進んでいたことでしょう。まさに
Think Global , Act Local
を誰よりも早く実践していたと思います。つまり異文化にむやみに抵抗しないばかりか、納得したら素直に受け入れる素地もあったと考えます。そして、前に記述しましたようにOwnershipで全社員が自分たちのものとして計画から実行まで自らが実践したと思います。
私の興味があるのは、いろいろと紆余屈折の社内での議論を経て今後の自社の行く道が“サービス業”だと結論付けた、その発想の源泉に迫りたいです。
また今回の成功は会社の規模や業種にも関係したのではとも思ったりします。
創業者社長の人間性の影響が及ぶ規模、そして通信サービス業界という成長産業にいたこと。これらがあいまって成功を加速したと思う面もあります。
この問いにどう答えてもらえるのか、その答えの内容に興味があります。
友人が顧問をしている会社の社長さんの著書を頂戴し、その読後感をメモにしてみました。
非常に勉強になるいい機会をありがとうございました。
仙石 通泰著 (かんき出版)
社員の「1行報告」が会社を変える
2008年09月19日
無料相談会とセミナ
全体としては、いろいろなところで開催されていると思います。弁理士会九州支部、各県の発明協会、各県、商工会議所、九州経済産業局などにお問い合わせ下さい。
そろそろ、年度後半に入ってセミナの開催も増えてきますので、講師をお引き受けすることも多くなってきそうですが、頑張っていこうと思います。
ご無沙汰でしたので、近況報告でした。
2008年09月19日
手作りジャム
”ボストン同様秋の足音が聞こえ始めた軽井沢から、遅ればせながらT家の果実畑の実りをお贈りいたします。毎年ご好評をいただいております母の手作りのジャムですが、今年は果実とてんさい糖(ビートが原料)のみでつくり、さらにヘルシーで自然の味を楽しんでいただけるよう工夫いたしました。旬の恵みを是非ご賞味ください。・・・・“
昨日上記の手紙が添えられた小さな箱詰めのジャムが宅急便で届きました。
年中行事になった友人のTさんからの贈り物は、我が家の楽しみの一つになっています。
そしてその味を楽しみながら軽井沢やボストンに思いをはせ、メモリーから出てくるままに一つ一つ話題にし過ぎ去り行く夏を、夫婦で振り返るのが恒例になっています。
そしてまた衣替えとともに気分も新たに年末に向け歩みだす時期でもあります。
14日の中秋の名月は楽しまれましたか? ブラックベリーとブルーベリーの写真をながめ虫の音に耳を傾けながら秋の夜長に一献傾けるのはいかがでしょうか。
2008年09月17日
9・11

今年もせみ時雨の中、7年経過した9・11を迎えました。
この日私の知人で、在京米国企業トップの人が社員に向けてメッセージを送りました。
ぜひ皆さんにも読んでいただきたいと思いましたので、ご本人の承諾を得て掲載します。
和訳もあわせご提供いただきました。
(一部固有名詞等は削除ないし変更しています)
【原文】
This morning instead of walking to the office, a recent activity that I have undertaken, I rode the subway. I enjoy my walks because of the solitude of just following a preplanned route and not having to spend a lot of time thinking about crowded or overheated subway cars or being pushed against people that I have never met or perhaps never will.
This morning was different on the Subway. It was not so crowded and I had time to observe the different people standing and sitting. There was a young man, mid 20?s with his face down apparently asleep from a long night out. There were two young girls going to elementary school, smiling, holding hands wearing their freshly laundered uniforms chatting away with each other. A mother was with a young boy sitting quietly next to her.
She also held a baby wrapped tightly in a scarf against her body. Two young girls were staring into mirrors, fixing their bangs and makeup. And also an assortment of salarymen reading their newspapers or novels or just perhaps staring at the pages.
As I exited the train a strange thought came to my mind. I asked myself "What if as I exited the station there was a loud explosion and the train that I was on was gone because of either an accident or act of terror?"
Of course I would be impacted by this event. Perhaps, I would be scared, shaken up afraid to go into a subway for a while. I also thought I would feel grateful that I had not been on that ill fated subway car. I would probably watch the event over and over on the evening news and see the faces of the same people that I saw on the subway continuously flashed on the evening news. But what about those faces, who were they and what would their death mean to me? Although I would mourn for their loss, I really did not know them.
When I was in high school we were required to memorize famous prose. One sentence written by John Donne was sealed into my memory by the repetitions required to memorize it. "any man's death diminishes me, because I am involved in mankind." Today I wondered how my life would be diminished without ever knowing the people on the subway car that I rode.
Maybe it would be, maybe not.
Seven years ago on September 11 an event conceived in evil, ended the lives of 176 our colleagues. You may ask yourselves who were they and why should you care? Remembering 9/11 may just be an our company ritual of remembrance that happens each year at this time. After all they too were only like
the people on the Subway we rode with this morning. Students and teachers, young mothers who were the sole support of their children, husbands, wives, grandparents? just ordinary people. Or if we choose to look closer into the lives of those who died September 11 or in my imaginary event today will we discover that they were in fact extraordinary individuals whose very existence had some small impact on our lives or because of their uniqueness in how they think, how they create or empower they may have dramatically changed the course of our lives had a tragic event not occurred. I prefer to believe the latter. We
are not castles surrounded by impenetrable walls and impassable moats.
It is through the vast array of interdependencies both observed and hidden that we both exist and evolve. By taking time to remember the people we know and learning and caring about the people we only read or hear about in the news can this chain called life evolve and create a better world for us and our children.
So each year at this time, I take the time to remember our colleagues from
9/11 because in their memory I have learned to care about the lives of the subway passengers and know that I would be less without them.
W.S (signed)
【和訳】
みなさまへ、
今朝、私は最近の日課に背き、歩いてオフィスに向かうのではなく、地下鉄に乗る
ことにしました。 混み合う蒸し暑い電車の中、見ず知らずの、そして二度と会う
ことのない人々にぴったりとくっつくこともなく、決まった道を1人で歩くのが好
きなのです。
でも今朝の電車は違いました。車内はそう混んでおらず、立っている人や座ってい
る人を観察する時間がありました。20代の、昨晩遊び疲れたであろう男性が、俯
き眠りこけていました。パリッとアイロンのきいた、洗ったばかりの制服を着た小
学生の女の子が2人、登校中、楽しそうに笑いながら、手をつないでおしゃべりし
ていました。 静かに座る幼い男の子を横に座らせた母親は、スリングに赤ちゃん
をすっぽりくるみ抱いていました。若い女の子2人は、鏡を覗き込み、前髪や化粧
を直していました。もしかしたらただページを見つめていただけかもしれませんが
、たくさんのサラリーマンも新聞や小説を読んでいました。
電車を降りる時、不思議な思いが湧き上がってきました。 "もし駅を出る時に、事
故かテロによる大きな爆発があって、自分が今まで乗っていた電車が吹き飛ばされ
たらどうなるだろう?"
もちろん自分はその事件に影響を受けるでしょう。ひょっとしたら、あまりの恐怖
に、再び地下鉄に乗れるようになるまで時間がかかるかもしれません。ちょうどそ
の不運な車両に乗っていなかったことに心の底から安堵するとも思います。夜のニ
ュースで、何度もその事故場面を見ては、車両で乗り合わせた人々の顔を思い浮か
べると思います。しかしその人たちの顔にどんな意味があるのでしょう?彼らは誰
で、彼らの死は、私にとってどういう意味があるのでしょうか?もちろん彼らの死
を悼みますが、知り合いという訳ではなかったのです。
私が高校生だった時、有名な散文を暗記させられました。何度も暗記させられたこ
とで、ジョン・ダンの一節を忘れることができなくなりました。 "誰が逝くも、これに
よって自らが死に往くに等しい。何故ならば、我もまた人類の一部であるが故
に" 今日、同じ車両に乗り合わせた人々を永遠に知ることなく、どうやって自
分自身の命もまた削られることになるのか考えていました。削られるのかもしれな
いし、削られないのかもしれない。
7年前の9月11日、悪意に満ちた事故によって、176名の同僚社員が犠牲
になりました。貴方は、"それ誰?どうでもよくない?"と言うかもしれません。9
・11を思い出すことは、毎年この時期に行う恒例のわが社の追悼儀式のような
ものかもしれません。結局のところ、彼らもまた、私たちが今朝地下鉄ですれ違っ
た人々と同じなのです。生徒や教師、子供を1人で養う若い母親達、夫、妻、祖父
母・・・ごく普通の人々です。 あの9・11で亡くなった人々の人生を掘り下げ
て見ることが、又は今日の私の地下鉄における想像で、乗客は事実、各々非凡で
あり、その存在が我々の人生に幾許かの影響を与えていたことに気づくことが、又は
彼ら1人1人の独自の考え方、創造性、そして彼らの与える力によって、我々の人
生航路が大きく変えられることがあるという事実が、悲劇を未然に防いだのかも知
れません。私は後者であると信じたいのです。
私達は難攻不落の壁や、決して渡れない堀に囲まれているわけではありません。
目に見える、または隠された様々な相互依存の関係により我々は存在し、進化して
いるのです。亡くなった人々を思い出したり、ニュースで見たり聞いたりするだけ
の人達を知り、その人々を気にかけることで、命と呼ばれるこの絆が未来に繋がり
、あなたや私達の子供達にとってより良い世界を作り出すことができるのです。
ですから毎年この日、私は9・11で犠牲になった同僚達を思い出すことにしています。
彼らを追悼することで、地下鉄で乗り合わせた人々の人生を思いやること、そして
彼ら無しでは自分の人生も欠けてしまうことを覚えたのです。
W.S.(サイン)
そしてこれを読んだ社員の家族の感想を添えます。
感想や意見を述べてもいいいの? 人は、稼ぐだけでなにごとにも、最近は無関心になり、自分の利害関係者だけの仲間で集まり、世の中、世界、あらゆる人々、動物やすべての生き物が、どのように自分と関わっているかなど、物事を深く考えなくなっているみたい。 W.Sさんの切実なる人へのおもいやりを忘れてほしくないためにも、あえて、無駄に大切な人の命が、消えしまうこと、そして、無駄に消えなくてもすむ知恵や、事を起こす相手かたの考えをしり、理解し合うことで、大切な命を失わなくて済むかもしれないとかんがえさせられるね。そして、知らない人というけど、ひとはしらなくても、自分や、家族、友達とかぞえたらきりない輪があるはず。決して、名前をしらないからというだけで、自分と関係ないと思うようになってる最近の人びとの心が、病みはじめているのね。大切な仲間関係を常に心にとめて、今、この悲しいことを教訓として、会社のたった小さな組織の仲間をしり、大切仲間意識をこの機会に、考え、大切にしてほしいと願っていらっしゃるのではないかしら。とても素晴らしいメッセージね。
一社員の家族
2008年09月16日
男女共同参画推進への取り組み

「優秀な女性職員の採用拡大に向けた取り組みを強化し、大卒以上の採用において研究職、技術職の女性採用比率を 13%以上とする」という目標を定めました。
「女性職員の活用に係る理解促進や、女性職員のキャリアコンピテンシー(自律的なキャリア形成力)を向上する策を講じていきます。具体例としては、キャリアコンピテンシー向上に係る主要策の一つであるメンター制度について、平成 21年度までに整備する。」という目標を定めました。
平成20年3月、男女共同参画の実現を現在の重要な経営課題として捉え、積極的かつ計画的に男女共同参画を推進していくために「原子力機構男女共同参画推進目標」を定めました。
以上は独立行政法人日本原子力研究開発機構の最近の広報誌(JAEAニュース第24号4ページ)から原文のまま引用いたしました。
戦後わが国の原子力開発が再開して50年以上の年月がたち、電力発電も原子力に40%以上依存するまでになりました。女性の活躍をますます期待する声とともに、いよいよ採用も本格化し、キャリア形成はじめ数々の手立てを講じ、制度や環境を整備していくことは朗報といえましょう。
同誌ではメンター制度にも言及しています。
メンター制度は、直属の上司による業務上の指導とは別に、メンター(よき指導者)が後輩職員であるメンティー(助言を受ける者)から話を聴き、日常における不安解消および成長の支援を行う制度であり、、、、、。
メンター(あるいはメンタリング)がこのようにいろんな場面で実効的に生かさせていることに、改めてその重要性を認識させられました。
それにしても女性採用比率13%はどのように理解したらいいのでしょうか。
2008年09月11日
黄金町バザール
本日9月11日から『黄金町バザール』が開催されます。
黄金町バザールは、まち全体を会場に、アーティストの空間と期間限定のショップが軒を並べて出現する楽しく回遊出来るまち並み作りを目標にしたイベントです。
黄金町は、かつて違法な特殊飲食店が軒を連ねていた街のようで、黄金町バザールは、街並みを新しく生まれ変わらせる事業の第一歩だそうです。
このイベントのディレクターは、FBCCに入居していただいているAPL(アイランドシティ・アートプロジェクト・ラボ)の代表の山野真悟氏です。
場所は、横浜市の京浜急行日ノ出町駅から黄金町駅の間の高架下、周辺空き店舗などです。
私も来週見に行く予定です。
「地域とアートの共存を通して街並みが新しく生まれ変わる
 」 ワクワクする取り組みです。
」 ワクワクする取り組みです。みなさんも是非、横浜方面に行くときにチョットだけ足を伸ばしてお立ち寄りください。
2008年09月09日
先端研究最前線

MIT の工学部長(Dean of Engineering)に1861年建学以来はじめてアジアから選ばれたSubra Suresh教授に先月東京で会う機会があり、そのとき話をされた内容の一部を紹介します。
MITにおける先端研究は
• 既成学問分野間の摩擦も無くhas no disciplinary constraints
• 高次元の複雑な、マクロの問題をis defined by highly complex, “macro” problems
(energy, environment, human diseases, …)
• グローバルのチーム編成でwill be shaped by global teams
• 人口増加に伴う経済発展を常に頭においてwill be influenced more strongly by
emerging economies with large population
設定したテーマを遂行していきます。
主要な研究対象はKey intellectual thrusts
• 多岐、多分野にわたるものでMultidisciplinarity
- エネルギーEnergy
- 地球の環境保全Global environmental sustainability
- 情報通信技術Information and communication technologies
- 工学、生命科学、医学、公衆衛生の融合Intersections of engineering,
life sciences, medicine and public health
が挙げられます。
アトムからシステムへ、ナノからマクロへのキャッチフレーズに表現されますように色々な分野の考え方を統合した方法で研究を進めます。Atoms to Systems, Nano to Macro - Integrated approach
具体的なテーマには
• 交通・運輸Transportation
• 水Water
• 数値計算、最適化と経済学Computation, Optimization and Economics
• がんとナノテクCancer Nanotechnology
• 環境保全のための物質・材料Materials for environmental sustainability
などがあります。
MITがフランスのパスツール研究所と共同でマラリアの撲滅にチャレンジしている例もあります。
Suresh教授が提起されたように今世界には人類にとって待ったなしの課題が山積しています。
アジアには鳥インフルエンザのようにいくつか挑戦すべき問題があります。アジアに近い九大をはじめとした九州の大学がアジア諸国の大学・研究機関と連携しアジアの人たちのため、ひいては地球全体のためにひとつひとつそれらの問題を解決してゆく道を真剣に探るべき時期が来ていると思うのは私だけでしょうか。