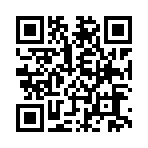2008年09月09日
先端研究最前線
-The Emerging Research Frontier

MIT の工学部長(Dean of Engineering)に1861年建学以来はじめてアジアから選ばれたSubra Suresh教授に先月東京で会う機会があり、そのとき話をされた内容の一部を紹介します。
MITにおける先端研究は
• 既成学問分野間の摩擦も無くhas no disciplinary constraints
• 高次元の複雑な、マクロの問題をis defined by highly complex, “macro” problems
(energy, environment, human diseases, …)
• グローバルのチーム編成でwill be shaped by global teams
• 人口増加に伴う経済発展を常に頭においてwill be influenced more strongly by
emerging economies with large population
設定したテーマを遂行していきます。
主要な研究対象はKey intellectual thrusts
• 多岐、多分野にわたるものでMultidisciplinarity
- エネルギーEnergy
- 地球の環境保全Global environmental sustainability
- 情報通信技術Information and communication technologies
- 工学、生命科学、医学、公衆衛生の融合Intersections of engineering,
life sciences, medicine and public health
が挙げられます。
アトムからシステムへ、ナノからマクロへのキャッチフレーズに表現されますように色々な分野の考え方を統合した方法で研究を進めます。Atoms to Systems, Nano to Macro - Integrated approach
具体的なテーマには
• 交通・運輸Transportation
• 水Water
• 数値計算、最適化と経済学Computation, Optimization and Economics
• がんとナノテクCancer Nanotechnology
• 環境保全のための物質・材料Materials for environmental sustainability
などがあります。
MITがフランスのパスツール研究所と共同でマラリアの撲滅にチャレンジしている例もあります。
Suresh教授が提起されたように今世界には人類にとって待ったなしの課題が山積しています。
アジアには鳥インフルエンザのようにいくつか挑戦すべき問題があります。アジアに近い九大をはじめとした九州の大学がアジア諸国の大学・研究機関と連携しアジアの人たちのため、ひいては地球全体のためにひとつひとつそれらの問題を解決してゆく道を真剣に探るべき時期が来ていると思うのは私だけでしょうか。

MIT の工学部長(Dean of Engineering)に1861年建学以来はじめてアジアから選ばれたSubra Suresh教授に先月東京で会う機会があり、そのとき話をされた内容の一部を紹介します。
MITにおける先端研究は
• 既成学問分野間の摩擦も無くhas no disciplinary constraints
• 高次元の複雑な、マクロの問題をis defined by highly complex, “macro” problems
(energy, environment, human diseases, …)
• グローバルのチーム編成でwill be shaped by global teams
• 人口増加に伴う経済発展を常に頭においてwill be influenced more strongly by
emerging economies with large population
設定したテーマを遂行していきます。
主要な研究対象はKey intellectual thrusts
• 多岐、多分野にわたるものでMultidisciplinarity
- エネルギーEnergy
- 地球の環境保全Global environmental sustainability
- 情報通信技術Information and communication technologies
- 工学、生命科学、医学、公衆衛生の融合Intersections of engineering,
life sciences, medicine and public health
が挙げられます。
アトムからシステムへ、ナノからマクロへのキャッチフレーズに表現されますように色々な分野の考え方を統合した方法で研究を進めます。Atoms to Systems, Nano to Macro - Integrated approach
具体的なテーマには
• 交通・運輸Transportation
• 水Water
• 数値計算、最適化と経済学Computation, Optimization and Economics
• がんとナノテクCancer Nanotechnology
• 環境保全のための物質・材料Materials for environmental sustainability
などがあります。
MITがフランスのパスツール研究所と共同でマラリアの撲滅にチャレンジしている例もあります。
Suresh教授が提起されたように今世界には人類にとって待ったなしの課題が山積しています。
アジアには鳥インフルエンザのようにいくつか挑戦すべき問題があります。アジアに近い九大をはじめとした九州の大学がアジア諸国の大学・研究機関と連携しアジアの人たちのため、ひいては地球全体のためにひとつひとつそれらの問題を解決してゆく道を真剣に探るべき時期が来ていると思うのは私だけでしょうか。
Posted by ayamizu at 10:40│Comments(0)
│空を飛んだ目黒の秋刀魚